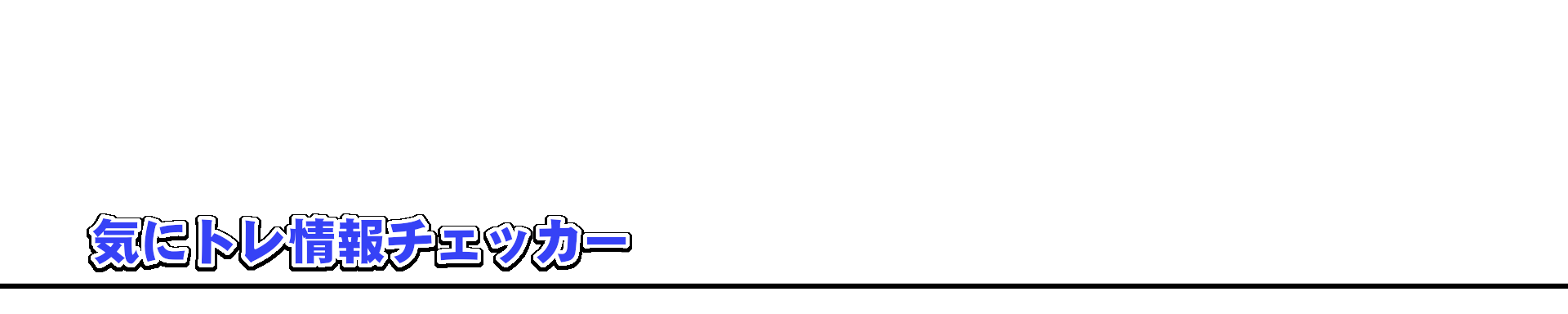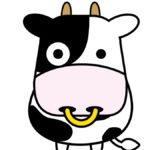6月の最終日の30日は大祓(おおはらえ)の日だそうです。
大祓とは、日本神道の除災行事のこと。
「悪いことが起きませんように」
と神様に祈りをささげるワケですね。

日本では6月30日と12月31日、年二回行われます。
6月30日に行われる大祓は、別名・夏越の祓(なごしのはらえ)とも言います。
“なごし”という呼び方から、名越と漢字で書くこともあります。
苗字が名越の人は、先祖が神社系の人である可能性があるかもしれませんね。
■大祓の詞(おおはらえのことば)の意味
大祓の詞とは、祝詞(のりと)の一つです。
祝詞とは仏教で言う“お経”みたいなもの。
お坊さんがお経を唱えるように、神職の人は大祓の日に大祓の詞を唱えるのです。
大祓の詞は、お経と比べると短いですが、そこには日本の神の話が詰め込まれています。
こちらのサイトに、大祓の詞と解読訳が書いてあります。
ご参考までにどうぞ。
大祓の詞は、前段と後段があり、前段は神話で、後段は助言に近い意味があると私は考えています。
こうこう、こうすれば、○○の神が□□してくれて、◆◆となるだろう。
といったような感じの内容と思えました。
前述のサイトの解読訳が正解でしょうが、小中学生などの子供が内容を把握するには、ちょっと難しいかもしれませんね。
■大祓が行われる神社

有名で大きな神社なら、大体は大祓の行事を行うと思います。
メジャーなところだと、関東の鶴岡八幡宮や東京大神宮、神田明神などが有名ですね。
東海では伊勢神宮、熱田神宮などが有名ですね。
岐阜の上野八幡神社(美濃市)でもするそうです。
大阪だと、服部天神宮などが有名なんじゃないかと思います。
多分、○○神宮という名前のところなら、大祓を大々的に行うんじゃないでしょうか。
皆さんの家の近くの神宮を調べてみてください。
何らかの形で大祓をやってると思います。
では、今回はこの辺で。
■関連項目

日本の記念日一覧(1月1日~12月31日)
日本の記念日の一覧です。1月1日から12月31日までの暦の順番です。ただし、日にちが変動する二十四節気や雑節そのもの(立春、入梅など)は割愛しています。空欄の日は、判明次第、追加していきます。■1月の記念日1月1日 元日(正月三が日の初日)...