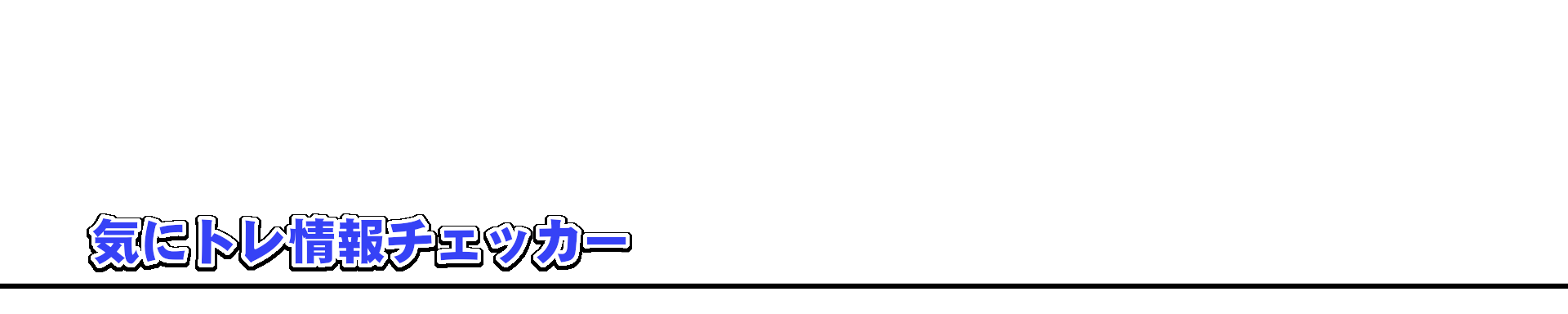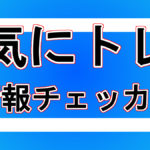たまに、ニュースなどで報道される気象現象に、
霰(あられ)、雹(ひょう)、霙(みぞれ)があります。
いずれも、雲から降り注ぐ氷の粒のようなものですが、これら3つには明確な違いがあります。
「字が違う」というのは却下です。(苦笑)
■霰と雹の違いは「粒の大きさ」と「形」

霰は、直径1〜5mmの氷の粒で構成されていて、形状は球形や円盤状など不規則な形をしています。
粒が小さいため、降り注いだ際には柔らかい感触があり、パラパラとした軟らかい音がします。
小さくて軽いため、人間社会に被害をもたらすことは稀です。
雹は、直径が6mm~1cm以上になることが多く、大きなものでは5cm以上になることもあります。
表面が凸凹した球形や卵形をしており、氷の粒というよりも「氷塊」に近いイメージです。
そのため、雹は霰よりも遥かに重くて硬く、落下速度が速いため、自動車のボンネットをへこませたり、家屋の瓦などを割ったり、人や動物に打撲傷を与え、農産物を破壊するなど、大きな被害を与えることがあります。
ゆえに、降り注いだ際には硬い感触があり、ゴツゴツとした大きな音がします。
霰と雹は、どちらも雲の中で水蒸気が凝結してできた雲粒が上昇気流に乗り、下降気流と寒冷層で衝突して通過することで凍りついたものです。

霰の場合は、氷の粒が下降気流ですぐに下に落下するため、粒は小さいままです。
一方で、雹の場合は、凍った粒がすぐに下に落ちずに雲中で上昇と下降を繰り返し、氷晶が衝突して結合することで、粒がより大きく、硬くなります。
故に、1cm以上の大きな粒になるのです。
■霰と雹の発生時期と地域の傾向の違い
霰と雹の違いは、大きさや形状だけでなく、時期や地域にも違いがあります。
◆発生時期の傾向の違い
霰は、通常では、冬季の降雪や雷雨の前に降りやすい傾向にあります。
雹は、通常では、夏季の雷雨の前に降りやすい傾向にあります。
あくまでも傾向であって、他の季節でも雹や霰が降ることがあります。
日本の夏季では、空気中の水分量が冬と比べて多い傾向にあるので、大きな塊になりやすいと言われています。
また、雹が発生する条件は、上昇気流の強さや温度などが影響するため、地域や季節によって発生頻度が異なることがあります。
◆発生地域の傾向の違い
霰は一般的に寒冷地域でよく見られます。
雹は温帯地域や熱帯地域で、より頻繁に発生します。
あくまでも傾向であり、寒冷地で雹が降ったり、温帯・熱帯地域で霰が降ったりすることもあります。
■霙(みぞれ)とは?
霰と雹の違いはわかりましたが、じゃあ「霙」(みぞれ)とは何なのか?
霙(みぞれ)とは、
雨と雪が同時に降ってくる現象
のこと言います。

霙のメカニズムを簡単に言うと、
本来は雪として降ってきたものの一部が、降ってくる途中で溶けて雨になることで起きる現象です。
つまり、雪のまま降ってくるものと、溶けて雨になって降ってくるものが混ざって同時に降ってくるということです。
そのため、ぱっと見では霰や雹と見間違われることがありますが、硬さや粒の形状が全く違うため、すぐに霙と再認識されることが多いです。
■まとめ
こんなところですね。
霰、雹、霙の違いをまとめると以下のとおりです。
- 霰は1~5mmくらいの氷の粒
- 雹は6mm以上の氷の粒で、5cmくらいになることもある。
- 霰は冬に発生しやすい傾向がある。
(それ以外の季節でも降ることがある。) - 雹は夏に発生しやすい傾向がある。
(それ以外の季節でも降ることがある。) - 霰は寒冷地で発生しやすい。
- 雹は温暖地域や熱帯地域で発生しやすい。
- 霙は、雨と雪が同時に降ってくる現象。
振ってくる雪の一部が途中で溶けて雨になることで発生する。
以上のように、霰と雹は氷の粒のが降る気象現象であることは共通していますが、その形状、サイズ、硬度、発生要因、地域的な出現頻度などに違いがあるのです。
まあ、粒が小さいのが霰で、粒が大きいのが雹と覚えておけば間違いありません。
霙は、「雨と雪が同時に降る」と覚えればOKです。
では、今回はこの辺で。