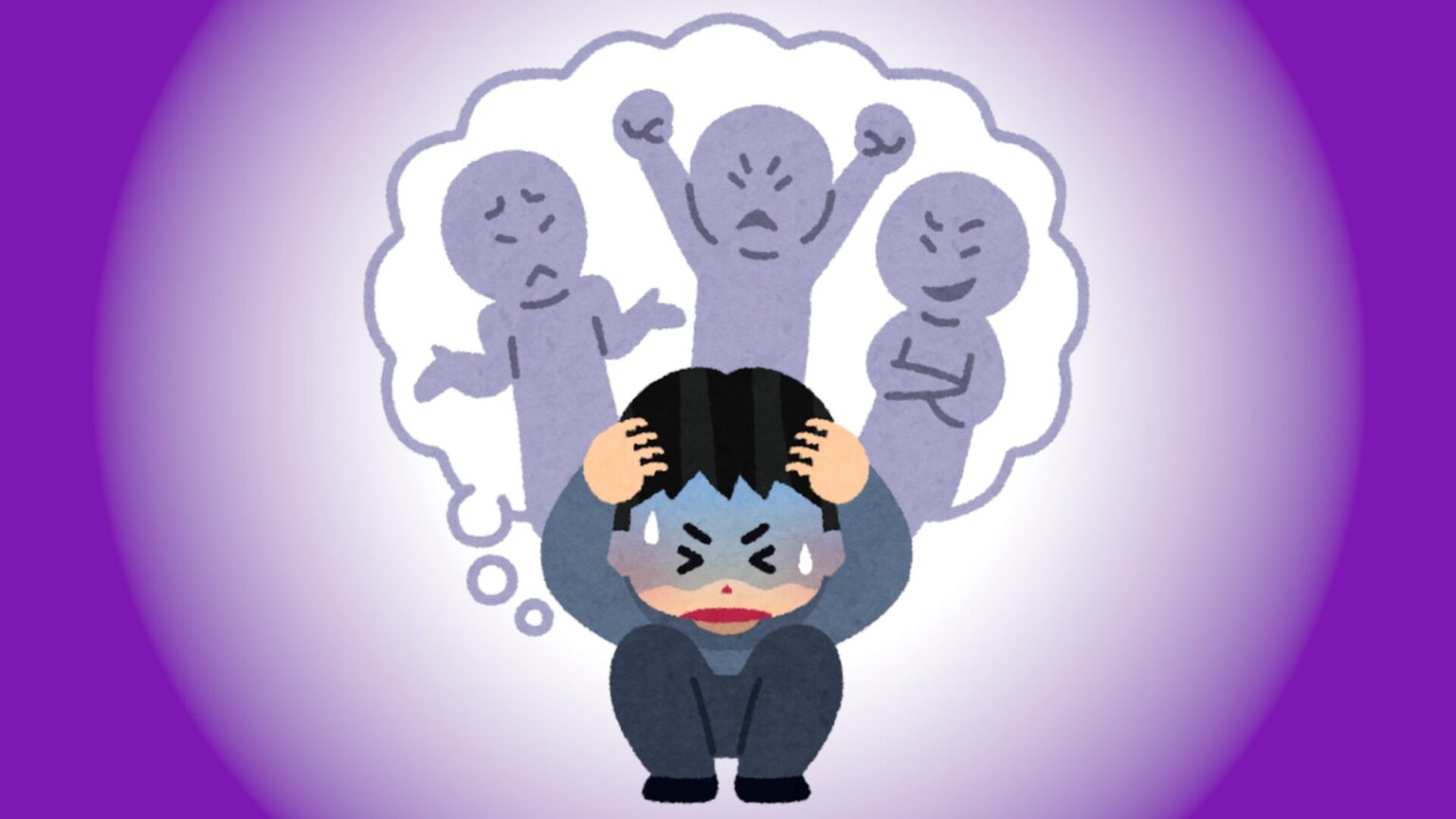被害妄想にとらわれた精神状態
のことである。
日本語では、妄想症または偏執病とも言う。
特に、被害妄想や関係妄想が中心となることが多く、論理的な思考は保たれているにもかかわらず、その妄想に基づいて行動する点が特徴である。
以前は独立した精神疾患として扱われることもあったが、現在では統合失調症スペクトラム障害や妄想性障害の一部として理解されることが一般的である。
■パラノイアの主な症状
パラノイアの症状は多岐にわたるが、主に以下のような妄想が見られる。
◆被害妄想
他者から危害を加えられている、だまされている、監視されているなどと感じる妄想である。
例えば、近所の人が自分の悪口を言っている、会社の上司が自分を陥れようとしているといった内容が挙げられる。
◆関係妄想
周囲の出来事や他者の言動が、すべて自分に関係していると感じる妄想である。
例えば、テレビのニュースが「自分のことを暗示している」、街中で聞こえる会話が「自分の噂話をしている」ように聞こえる、といった内容である。
◆誇大妄想
自分が特別な能力を持っている、非常に裕福である、重要な人物であるなどと過大に評価する妄想。
似たような症状に、思春期に発症する“中二病”がある。
(中二病は俗称・通称であり、そのような病気や疾患は存在しない。)
◆嫉妬妄想
根拠がないにもかかわらず、パートナーが浮気をしていると確信してしまう妄想。
以上、これらの妄想は、患者さんにとっては現実と区別がつかないほど確固たるものであり、論理的な説得では動かせないことが多いである。
■パラノイアの原因
パラノイアの原因は単一ではなく、以下のような複数の要因が絡み合っていると考えられている。
◆生物学的要因
脳の神経伝達物質の異常(ドーパミンの過剰など)が関連している可能性が指摘されている。
また、遺伝的要因も一部関与すると考えられている。
◆心理的要因
ストレス、トラウマ体験、自己肯定感の低さなどが、妄想の形成に影響を与えることがありえる。
◆社会的要因
社会的孤立、人間関係のトラブル、文化的背景なども影響を与える可能性がある。
◆身体疾患・薬物
特定の身体疾患(例:認知症、脳腫瘍)や薬物の使用(例:覚醒剤、ステロイド)によって、パラノイア様の症状が現れることもある。
■パラノイアの診断と治療
パラノイアの診断は、精神科医による詳細な問診や精神状態の評価に基づいて行われる。
他の精神疾患や身体疾患の除外も重要である。
治療は、主に以下の方法が用いられる。
◆薬物療法
抗精神病薬が症状の改善に有効な場合がある。
特に、妄想の内容を和らげたり、興奮状態を鎮めたりする効果が期待されている。
◆精神療法
妄想そのものを直接修正することは難しいとされているが、妄想によって生じる苦痛や不安を軽減し、現実との折り合いをつけるためのサポートを行う。
その際に、認知行動療法が用いられることもある。
◆環境調整
ストレスの軽減や安定した生活環境の確保が、症状の悪化を防ぐ上で重要である。
■パラノイア患者の周囲の対応
パラノイアの症状を示す人への対応は、非常にデリケートな問題である。
◆妄想を否定しない
妄想を真正面から否定したり、説得しようとしたりすることは、多くの場合逆効果であり、関係を悪化させる可能性があります。
◆共感を示す
妄想の内容そのものに共感するのではなく、妄想によって本人が感じている苦痛や不安な気持ちに寄り添い、理解しようとする姿勢が大切である。
◆安全を確保する
妄想によって、本人や周囲の安全が脅かされる可能性がある場合は、専門家や関係機関に相談し、適切な介入を検討する必要があります。
専門家への相談を促す: 早期に精神科医や精神保健福祉士などの専門家への相談を促すことが重要である。
パラノイアは、本人にとって非常に辛い精神状態であり、周囲の理解と適切なサポートが不可欠である。
■関連項目
なし