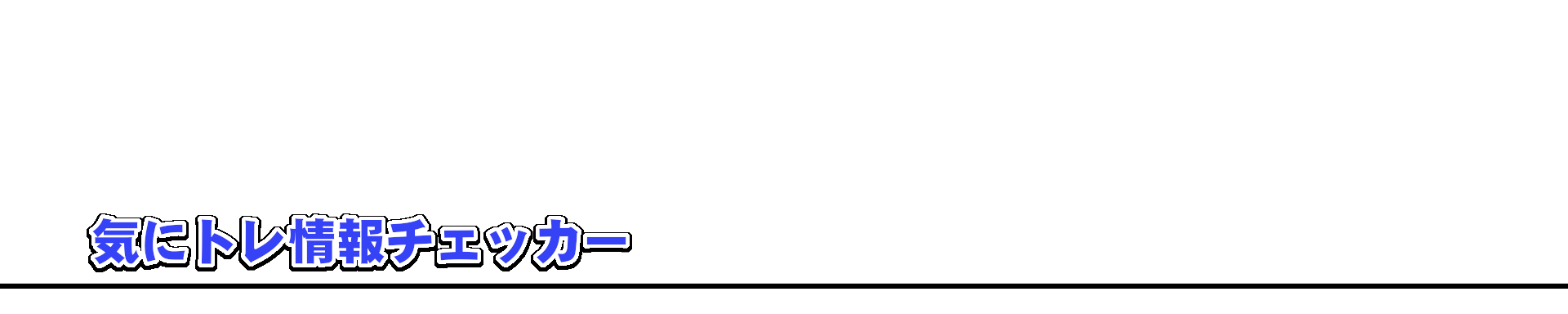強度行動障害とは、自閉症や知的障害を持つ人に見られる、日常生活に著しい困難をもたらす行動の総称です。
具体的には、以下のような行動を突発的かつ頻繁に行います。
- 自傷行為(自分の頭を壁に打ち付ける、体を叩くなど)
- 他害行為(他人を叩く、噛みつくなど)
- 破壊行為(周囲の物を壊す)
- 不適切な場所での排泄
- 大声を出し続ける、奇声を上げる
- 飛び出す
これらの行動は、本人の不快感や要求、感情をうまく伝えられないこと、感覚過敏や感覚鈍麻、環境の変化への不安などが原因で引き起こされると考えられています。
強度行動障害は、本人だけでなく、家族や支援者にも大きな負担をかけるため、適切な理解と支援が不可欠です。
■強度行動障害は生まれつきではない
強度行動障害は生まれつきではなく、二次的なものです。
発達障害を持つ人が、日常生活で困難を感じたり、周囲の環境が適切でなかったりする場合に、二次的に現れる行動とされています。
あくまでも、知的障害や自閉症などの発達障害がベースにあり、それらが原因で、周囲の人や物を傷つけたり、物を壊したりといった行動が頻繁に見られる状態のことを言います。
■強度行動障害の特徴
強度行動障害には、以下のような特徴が見られます。
◆自傷行為
自分の体を叩く、頭を壁に打ち付ける、体を噛む、皮膚を掻きむしるなど、自分自身を傷つける行動です。痛みを感じにくい、または痛みを感じることで安心感を得ようとすることが原因の一つとされています。
◆他害行為
周囲の人を叩く、噛みつく、引っかく、物を投げつけるなど、他者を傷つける行動です。
自分の要求が通らない、伝えたいことがあるのに伝わらない、不快な状況から逃れたいといった際に起こりやすいとされています。
◆常同行動
体を前後に揺らす、手をひらひらさせる、特定の音を出し続けるなど、同じ行動を何度も繰り返す行動です。
不安や緊張を和らげる、感覚的な刺激を求めることが目的と考えられています。
他人から見たら「ちょっとヘンなヤツ」と言った感じに映ります。
◆多動・飛び出し
常に動き回る、急に走り出す、どこかへ飛び出してしまうといった行動です。
衝動性が高く、危険な状況に身を置くリスクがあるため、注意が必要です。
場所によっては交通事故の原因になる可能性があり、非常に危険な行動とも言えます。
◆こだわり行動
特定の物や場所に執着する、決まった手順でなければ行動できない、予定が変わるとパニックになるなど、特定の物事に対する強いこだわりです。
不安な気持ちや混乱を避けるために、自分でルールを作り、それを守ろうとすることが原因とされています。
■強度行動障害の原因
強度行動障害の原因は一つではなく、様々な要因が複雑に絡み合っていると考えられています。
◆コミュニケーションの困難さ
言葉で自分の気持ちや要求を伝えることが難しいため、自傷や他害といった行動で表現しようとします。
自閉症スペクトラム障害者に多い傾向にあります。
◆感覚過敏・感覚鈍麻
光、音、匂い、触覚などの感覚が過敏であったり、逆に鈍麻であったりするため、周囲の環境に強い不快感や不安を感じることがあります。
◆環境の変化への適応の困難さ
新しい場所や人、日課の変化など、環境の変化に強いストレスを感じ、パニックになったり行動障害を引き起こしたりします。
適応障害と誤解されるケースもあります。
◆身体的な不調
痛みや不快感、空腹、睡眠不足などの身体的な不調が、行動障害の引き金になることがあります。
■強度行動障害への支援
強度行動障害への支援は、行動の背景にある原因を理解し、その人に合った方法で対応することが重要です。
◆環境調整
刺激の少ない落ち着ける環境を整える、日課を分かりやすく提示する、予測しやすい生活リズムを作るなど、本人が安心して過ごせる環境を整えます。
◆コミュニケーション支援
言葉以外のコミュニケーション手段(ジェスチャー、絵カード、写真など)を導入し、本人の気持ちや要求を伝えやすくします。
◆行動の機能分析
なぜその行動が起こるのか、行動の背景にある原因や目的を分析し、行動を減らすための具体的な支援策を立てます。
◆専門的な支援
行動障害専門の研修を受けた支援者が、行動障害の特性を理解した上で、適切な対応を行います。
強度行動障害は、適切な支援によって行動が落ち着き、本人や家族の生活の質が向上することが期待できます。
早期に専門機関に相談し、適切な支援を受けることが大切です。
■強度行動障害にとりくむ施設・事業所等
強度行動障害への支援は、その専門性の高さから、専門的な知識と経験を持つ施設や事業所が全国各地に存在します。
ここでは、厚生労働省などの公的な資料や各施設のウェブサイトなどで言及されている、強度行動障害に取り組んでいる施設や事業所の例をいくつかご紹介します。
※2025年8月4日時点での情報です。
あなたが閲覧した時点では、各団体や施設等の名称が変更、または移転・閉鎖されている可能性があります。
◆国立病院機構
強度行動障害を伴う患者への医療を提供している国立病院機構の施設があります。
国立病院機構肥前精神医療センター(佐賀県)
強度行動障害専門の病棟を持ち、医師、看護師、心理療法士、作業療法士、言語聴覚士など、多職種によるチーム医療を行っています。
国立病院機構やまと精神医療センター(奈良県)
重度の知的障害と行動障害を併せ持つ「動く重症心身障害」の方を対象に、専門的な医療・看護・療育面での支援に取り組んでいます。
国立病院機構さいがた医療センター(新潟県)
こちらも強度行動障害に対する専門的な医療を行っている施設として挙げられています。
◆公的機関・地域支援の取り組み
各自治体や公的機関でも、強度行動障害に対する専門的な支援事業が行われています。
大阪府砂川厚生福祉センター
強度行動障害の状態を示す方を対象とした特化型施設「いぶき」を運営し、有期限での集中的な支援を行っています。
名古屋市強度行動障害者支援事業
専門支援員を事業所に派遣し、支援に困っている現場の職員と協力して問題解決を模索するなど、地域での支援体制の構築に取り組んでいます。
福岡市障がい者地域生活・行動支援センターか~む
強度行動障害の方の一時的な受け入れ(緊急対応)や、福岡市内の支援者へのスキル向上を目指した事業を実施しています。
◆その他の取り組み
民間法人やNPO法人でも、強度行動障害に特化した支援を行う事業所があります。
社会福祉法人北摂杉の子会(大阪府)
強度行動障害専門のグループホームを開設するなど、障害特性に合わせた住環境の整備や支援モデルを展開しています。
社会福祉法人侑愛会(北海道)
有期限の「通過型」支援として、強度行動障害を持つ方を受け入れ、出身地へ戻るための支援を行っています。
■支援を受ける際の注意点
強度行動障害への支援は、本人の状態や生活状況、居住地域によって利用できるサービスや施設が異なります。
支援を検討する際は、まずお住まいの地域の市区町村の障害福祉担当窓口や、基幹相談支援センターに相談することをおすすめします。
そこで、本人の状況に応じた支援機関や、利用できるサービスについて情報提供を受けることができます。また、専門的な支援が必要な場合は、適切な医療機関や施設を紹介してもらえることもあります。
では、今回はこの辺で。