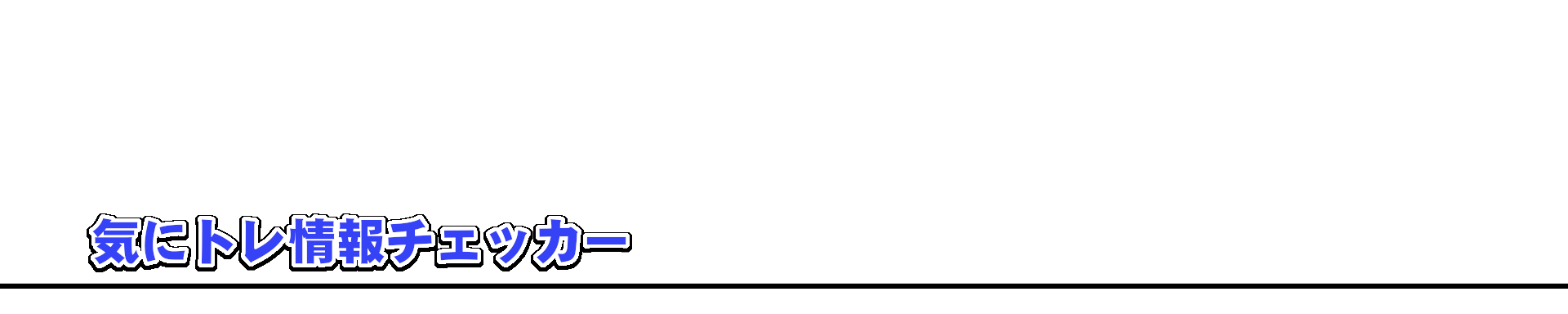■ちんすこうの日ってどんな日?
ちんすこうの日とは、沖縄の伝統的な焼き菓子「ちんすこう」を、沖縄の財産として未来に残すことを目的として作られた記念日です。
◆ちんすこう とは?
ちんすこうは、小麦粉、砂糖、ラードの3つのシンプルな材料で作られる、沖縄を代表する伝統的な焼き菓子です。
サクサクとした独特の食感と、素朴で優しい甘さが特徴です♪
■提唱・制定者は?
ちんすこうの日の制定者は、「沖縄県観光おみやげ品公正取引協議会」さんです。
沖縄県那覇市に事務局を置き、おみやげ品を対象とした景品類または表示に関する事項について、公正取引委員会と消費者庁の認定を受けて制定した「公正競争規約」を業者さんに周知徹底する活動を行っている機関です。
■日付の理由は?
日付の理由は、「ちんすこう」が地理的表示(GI)保護制度に登録となった日(2024年8月27日)から来ています。
■日本記念日協会に登録されているの?
ちんすこうの日は、日本記念日協会に認定・登録されています。
登録年月日は、2024年(令和6年)8月22日です。
■ ちんすこうの歴史と由来
◆琉球王国時代の高級菓子
ちんすこうの起源は、琉球王国時代にさかのぼります。
中国や日本の文化を取り入れながら、琉球独自の食文化が花開く中で誕生しました。
当時は、中国から来訪する冊封使や薩摩藩の役人をもてなすための宮廷菓子であり、王族や貴族だけが口にできる貴重なものだったそうです。
◆名前の由来
「ちんすこう」という名前には諸説あります。
・金楚糕(きんそこう)説
「金」は高価であることや、焼き上がりの黄金色を表し、「楚糕(すこう)」は菓子を意味するとされています。
・珍楚糕(ちんそこう)説
「珍しい、貴重なお菓子」という意味を持つという説です。
どちらにしても、ちんすこうがかつては特別な席でしか食べられない高級品であったことを示しています。
◆現在の形になるまで
当初のちんすこうは、米粉を使った蒸し菓子であったとされています。
明治時代に入ってから、レンガ釜で焼くようになり、現在のサクサクした食感になりました。
また、現在よく見られるギザギザの形は、第二次世界大戦後にアメリカ軍が使用していたクッキー型を転用して作られるようになったと言われています。
■ ちんすこうの素材の特徴と種類
◆基本的な材料
ちんすこうの基本的な材料は、小麦粉、砂糖、そしてラードです。ラードを使用することで、あの独特なサクサク・ホロホロとした食感が生まれます。
最近では、サラダ油などで代用して作られるレシピもありますが、本場の味を出すにはラードが欠かせません。
◆様々なフレーバー
伝統的なプレーン味の他に、現在では多種多様なフレーバーが販売されています。
・塩ちんすこう
沖縄の海塩(特に「雪塩」など)を使ったもので、甘さの中にほんのりとした塩気が感じられます。
・黒糖ちんすこう
沖縄の名産である黒糖を使ったもので、コクのある深い甘さが特徴です。
・紅芋ちんすこう
沖縄を代表する紅芋を使った、美しい紫色のお菓子です。
・その他
チョコレート、パイン、ココナッツ、抹茶、シークヮーサーなど、様々なアレンジが楽しまれています。
◆形と食感
現在の主流は、ギザギザとした細長い形ですが、琉球王国時代の名残で丸い形のものもあります。
また、食感もメーカーによって異なり、よりホロホロと崩れるタイプや、クッキーのようにしっかりとした歯ごたえがあるタイプなど、バリエーションが豊富です。
こんなところですね♪
ちんすこうは、そのシンプルな見た目とは裏腹に、琉球の歴史と文化が凝縮された、沖縄を代表する銘菓です。
お土産としてはもちろん、沖縄県民にとっても身近な存在として愛され続けているそうです。
知り合いがたまに沖縄に旅行に行った時に、よくお土産で買ってきてくれました。
クッキーよりも少し脆い感じがありましたが、独特の風味とサクサクの食感は、とても気持ちがよくなりますよ♪
では、今回はこの辺で。
■関連項目