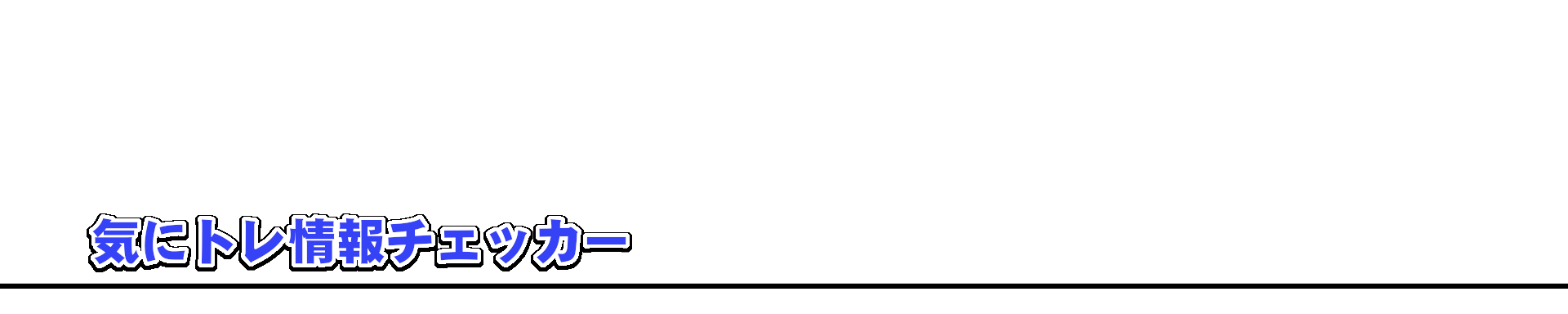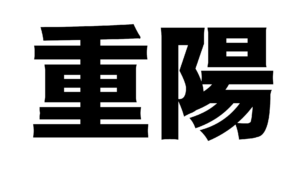重陽の節句の起源(由来)は、中国の陰陽説から来ています。
中国に伝わる陰陽説には、陽数(奇数)と陰数(偶数)があります。
陽数は縁起が良く、逆に陰数はあまり縁起が良くない数といわれています。
少し話はズレますが、漢字の画数にも陽数と陰数が関係しており、姓名判断では総画数が陰数だと良くないそうです。
(悪くない場合もあるそうですがw)
話を戻しまして・・・。
数は0から9までの数字で表記されています。
そのうち、9という数字は最も高い奇数です。
- 奇数=陽数
すなわち、9の陽数が重なる日、9月9日は非常にめでたい日ということなのです。
- 陽数が重なる日=重陽
というワケですね。
9が重なる日なので、別名、”重九(ちょうきゅう)“とも言います。
古代中国では、そんなめでたい9月9日を祝い、丁度この時期に咲く菊の花を酒に浮かべた菊酒を飲みました。
菊酒を飲むことによって、不老長寿と厄払いを願ったそうです。
それ故に、菊の節句とも呼ばれています。
確かに、お刺身などに添えられている食用の菊の花には殺菌効果があることが現代では証明されています。
なので、菊の花を酒に入れることで、食中毒の予防になっていたとも言えなくないですね。
そんな古代中国の習慣が日本に伝わり、朝廷の祝い事や武士の祝日となりました。
そして、現代の重陽の節句として、今日に至るのです。
以上が重陽の節句の起源(由来)です。
まあ、今日に至るといっても、知名度は極めて低い節句ですが。(苦笑)
それに、菊の花を酒に浮かべて飲む習慣は、既に廃れてしまってありません。
廃れてしまった最大の理由は、
- 旧暦から新暦に変わったことで、
菊の花が咲く時期とズレてしまった
ことにあります。
時期がズレてしまうと、当然、菊の花が手に入りません。
咲いてないんですから。
しかも、菊の花は昔は高価だったため、一般庶民が手に入れるのは経済的に厳しかったのもあります。
そんなワケで、菊酒を飲むことができなくなったため、重陽の節句という名前のみが現代に残っているのです。
しかしながら、重陽の節句が完全に廃れたワケではありません。
現在でも、一部の地域では、9月9日に栗ご飯を食べる習慣があります。
旧暦の9月9日は、新暦で言うと10月です。
10月は丁度、栗が収穫できる時期なので、飲めない菊酒の代わりに、栗ご飯を食べて無病息災を願ったのです。
その習慣が現代にまで残ったというワケですね。
「時期外れの高価な菊の花よりも、時期中に安価で大量に獲れる栗を使った方が、お祝いしやすい!」
という極めて現実的な理由から、栗ご飯を食べる習慣が生まれたんですね。
9月9日に限らず、秋には栗ご飯を食べる家庭が多いと思います。
栗ご飯を食べる際には、重陽の節句について思い出してほしいですね。
では、今回はこの辺で。
■関連項目